アントレプレナーシップとは?5つのスキルと考え方を紹介
2025/05/09
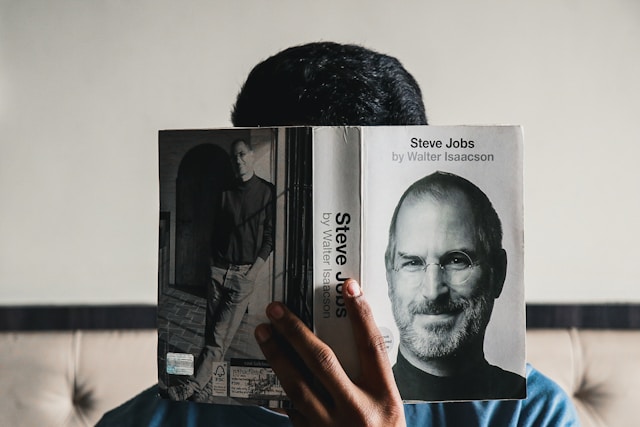
新規事業を進める上で必ず当たる壁の1つに、「新規事業の人材不足」があります。その背景にあるのが、起業家的マインド(アントレプレナーシップ)を持った“イントレプレナー”の不在です。
本記事では、企業内でアントレプレナーシップを持つ人材をどう育て、どう活用するかを明らかにしていきます。
アントレプレナーシップは、限られた人が生まれながらにして持つ才能ではなく、成果を生み出すための行動の「技術」です。技術ということは、誰でも学ぶことができ、習得することができるということです。
ゼロからの起業にも、大企業での新規事業立ち上げにも通用するアントレプレナーシップの本質的な考え方と実践手法を、早速見ていきましょう。
1. アントレプレナーシップとは?
1-1. アントレプレナーシップの定義
アントレプレナーシップ(Entrepreneurship)は、「起業家精神」とも訳され、新たなビジネスチャンスを見出し、社会的・経済的な価値を創出し、必要なリスクを引き受けながら行動を起こす姿勢だと言われています。
重要なのは、アントレプレナーシップは、才能ではなく、姿勢・マインドセットであるという点です。「できない理由」よりも「どうすれば可能になるか」を考えるマインドセットや、そのアイデアを実行に移す行動力という、自身の考え方やアクションなど、コントロール可能なことに目を向ける態度とも言えるでしょう。
現代の経営に多大な影響を与え、「経営学の父」とも称されるPeter Druckerが著書『Innovation and Entrepreneurship』の中で述べた、「イノベーションとは、何よりも“ひらめき”ではなく“実践”である。知識や独創性、そして集中力を必要とする地道な仕事なのだ。」(*1)という言葉も、世の中に大きな変革をもたらす起業家が持つアントレプレナーシップを象徴していると言えます。
1-2. アントレプレナーシップとイントレプレナーシップ
イントレプレナーシップとは、「組織内起業家精神」とも呼ばれており、企業内で起業家のように新しいアイデアを考え、実行する能力や姿勢です。新規事業のアイディアを見つけたり、新規事業を推進していく過程においてはイントレプレナーシップが不可欠です。
当社がグローバルで大手企業のイノベーション推進を支援を手がける中で感じていることは、イノベーション活動が進むか否かは、最終的には社内人材による事業のドライブ力(推進力)が重要だということです。事業のドライブ力を身につけるという意味では、優れた起業家が持つアントレプレナーシップから参考にすべきことが多くあるでしょう。
また、企業内でアントレプレナーシップを育むためには、人材開発も必要ですが、同じくらい風土改革や人事制度、評価制度の改革も欠かせません。
当記事後半では、イントレプレナーシップを育むための施策の提案や紹介も行いますので、新規事業推進事務局や大手企業の人材育成に関わる方も最後までご覧いただければと思います。
2. なぜ今、“アントレプレナーシップ”が企業内でも重要視されているのか?
アントレプレナーシップは、もともと起業家に必要な姿勢や思考法として語られることが多かった概念ですが、近年では企業の中で働く人材にとっても不可欠なマインドセットとして注目を集めています。
特に、大手企業が新規事業創出や事業ポートフォリオの再構築を迫られる現在、社内の人材が自ら課題を発見し、リスクを取りながら解決策を描く力=アントレプレナーシップは、企業の持続的成長のために避けては通れないテーマとなっています。
ここでは、その重要性が高まっている背景を、企業実務に直結する3つの観点から整理してみましょう。
2-1. 変化が激しい社会・ビジネス環境
いま、私たちを取り巻く事業環境は“VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)”と呼ばれる不確実性に満ちた状況にあります(*2)。テクノロジーによる業界構造の変化、気候変動や地政学リスクなど、多くの企業がこれまでの成功モデルを通用させづらい局面に直面しています。
このような環境下では、トップダウンによる一方向の変革ではなく、社員一人ひとりが自らの意思で変化をつくり出す姿勢が組織全体に求められています。新規事業の文脈でも、単に新しいことを“やらされる”のではなく、“やりたい”と動き出す人材をいかに増やせるかが、競争優位を分けるカギになるのです。
2-2. AI時代の価値創造と人材の越境
生成AIや自動化技術の進化によって、これまでの業務や判断が機械に代替されつつあるなか、企業における人材の役割も大きく変わろうとしています。これからの時代に価値を発揮する人材とは、「何をすべきか決められた人」ではなく、「何が価値となるかを自ら問う人」です(*3)。
アントレプレナーシップを持つ人材は、環境や与件が整っていない中でも、自ら問いを立て、アイデアを生み、仲間を巻き込みながら動き出すことができます。こうした人材を現場から育てる視点は、AI活用時代における企業競争力のコアになるでしょう。
2-3. 社会的インパクトと企業の役割拡大
スタートアップによる新市場の創出や雇用効果は、マクロ経済におけるアントレプレナーシップの重要性を物語っています。米国では新設企業が年間約300万人の雇用を創出しており、特にGAFAMのようなイノベーティブな企業は、GDP押し上げや技術革新の担い手として存在感を高めています(*4)。

日本においても、少子高齢化や地域経済の衰退といった課題に対して、既存事業の延長ではない、新たな価値提供の構想力が求められています。こうした文脈において、企業内の人材が“社会課題をビジネスで解決しようとする”意志を持つことは、企業の信頼や存在意義にも直結するのではないでしょうか。
3. 日本におけるアントレプレナーシップの現在位置
アントレプレナーシップの重要性が叫ばれる中、日本ではこの起業家的マインドを持ち、自ら事業を生み出す人の割合が、国際的に見てもまだ高いとはいえない状況にあります。これは、「人材がいないから」と一言で済ませられる問題ではなく、社会全体における文化や環境の違いが大きく関係しています。
企業の新規事業担当者として、このような現状を把握することは、「なぜ自社では挑戦する人が少ないのか」という問いに対するヒントにもつながります。
3-1 TEAスコアに見る日本の立ち位置
アントレプレナーシップの国際比較でよく用いられる指標に、GEM(Global Entrepreneurship Monitor)調査における*TEA(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity)(*5)があります。これは「起業準備中〜創業3.5年未満の起業家数が、全成人(18〜64歳)人口に占める割合」を示すもので、各国の起業活動の“実際の広がり”を定量的に把握できる指標です。

2018年における主要7カ国のTEAスコアは以下の通りです:
- 米国 15.6
- 中国 10.4
- イギリス 8.2
- フランス 6.1
- 日本 5.3
- ドイツ 5
- イタリア 4.2
ご覧のように、日本は5.3%と主要7か国中5位という位置にとどまり、アメリカ(15.6%)や中国(10.4%)と比べるとおよそ3分の1以下という水準にあります。
3-2 日本におけるアントレプレナーシップが低い背景
① ロールモデルの不在・起業家が身近でない
「過去2年以内に新しいビジネスを始めた人を知っている」と答えた人の割合は、日本ではわずか19.4%にとどまります。一方、アメリカでは30%以上の水準が一般的であり、起業が身近にあることで挑戦への心理的な障壁が低くなっていると考えられます。
② 起業=リスク、大企業=安定という社会観
GEM調査では、「起業を望ましい職業選択と考える人」の割合が、日本では22.8%とかなり低水準であることが報告されています。これは、大企業での就職・安定志向が社会的に根強い日本において、起業が“リスクある特別な選択肢”とみなされがちな文化背景を示唆しています。
③ 失敗への恐怖感の強さ
日本の“失敗脅威指数”は44.4%と、主要国の中でも高めの水準にあります(=起業しない理由として「失敗への恐れ」を選ぶ割合)。この傾向は企業文化にも投影されており、「うまくいかなかったらどうしよう」「失敗が評価に響くのでは」といった不安が新規事業へのブレーキになることもあります。
このように、国際比較の中で見えてくる日本の課題は、単に「人材がいない」という表面的な問題ではなく、挑戦を促す環境や文化、制度が十分に整っていないことに起因していることが分かります。

一方で、「アントレプレナーとは、生まれつきの才能を持ったごく一部の人たちがなるものでは?」といったイメージが、無意識のうちに私たちの認識を狭めている可能性もあります。そこで次章では、アントレプレナーに関する実証的な研究をもとに、「実は誰もがなり得る存在であり、育成が可能である」という視点から、アントレプレナーの意外な真実を紐解いていきます。
4. アントレプレナーの意外な真実
アントレプレナーというと、若く(時には在学中)から起業し、天才的な頭脳で一夜にして成功者に上り詰めたイメージがある方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、そのようなイメージは映画やメディアによってやや誇張されたものであり、アントレプレナーを対象にした研究では、そのようなイメージは必ずしも事実とは一致しないことがわかっています。つまり、アントレプレナーは成る可くしてなるのではなく育成できるということです。
ここでは、アントレプレナーの意外な真実を4つ見ていきます。
成功する起業家は決して若くない
一般的に、起業家と聞くと若者を思い浮かべがちですが、実際には中高年の起業家が成功するケースが多いことが研究で示されています。例えば、最も成長する企業の創業者の平均年齢は45歳であり、年齢が高いほど成功率が上昇する傾向があります(*6)。

これは、アントレプレナーが成功するには、若さやファーストペンギンであることよりも、ビジネスの経験を積んでおり、どのように事業を進めるべきかをわかっていることの方が重要であることを示唆しています。そのため、自分はもう若くないから、と言ってチャレンジを諦めるのは合理的に考えて合理的ではないでしょう。世界中の全ての人にとって、今日が残りの人生で一番若い日であり、何を始めるにしても遅すぎることはありません。
また、社内に若いアントレプレナーシップを持つ人材がいないからと言って、それも見方によっては、成功確率の高い経験豊富なビジネスマンが多くいると考えることもできます。
移民の起業家の方が成功しやすい
異なる視点や経験を持つ移民は、起業家精神が高い傾向があります。カウフマンの研究によると、米国において、移民が起業家になる確率は米国内で生まれた人と比較して、約2倍高いという調査もあります(*7)。

移民である彼らがアントレプレナーとして成功しやすいのは、新しい環境での適応力や当たり前だと考えられがちな前提を疑うことに長けているためだと考えられています。
つまり、他の人と違うということは、アントレプレナーシップという文脈では大きな武器であるということです。企業内においては、人と違うものの見方ができる人材や、異なるバックグラウンドを持っている人材が新規事業においては、大きな違いを生み出すかもしれません。
起業家精神は生まれつきではなく、獲得できるもの
アントレプレナーシップというと生まれつきのものだと考えられることも多いものです。ですが、アントレプレナーシップは冒頭でも説明したように姿勢・マインドセットや行動力などのコントロールできる要素から成り立っており、経験や教育を通じて育成可能であることが指摘されています(*8)。
そのため、自分には起業する才能がないと諦める必要はありません。誰もが人は生まれつきアントレプレナーになる素質があるのではなく、学びながらアントレプレナーになっていくのです。
起業家の成功と学歴の相関性
アントレプレナーというと、ハーバード大学などの一流大学出身の人が多いイメージがある方も多いでしょうが、起業家の成功と学歴との間には必ずしも強い相関関係がないことが研究で示されています。特に、性格や行動特性、経験など、学歴以外の要因が成功に影響を与えることが多いとされています(*9)。
一流大学が持つ人脈や投資に使える資金力が重要ではないというわけではなく、それよりもアントレプレナーとしてどう考えて行動するのか、という要素の方がより成功するための要因であるということです。
5. アントレプレナーシップを持つ人の考え方とスキル
アントレプレナーシップが獲得できるスキルであるということはこれまでも繰り返し述べてきました。では、アントレプレナーシップとは実際にどのようなスキルなのか、ここではアントレプレナーシップ教育で有名なアメリカのBabson Collegeが提唱する「Entrepreneurial Thought and Action(起業家的な思考と行動)」のメソッドから紐解いていきます。
新規事業推進にもゼロからの起業にも役立つ共通したアントレプレナーシップのスキルを5つ見ていきましょう。
不確実性をチャンスに変える思考法
ビジネスを始める際、多くの人が「リスク」や「不確実性」をネガティブに捉えがちです。しかし、アントレプレナーシップを持つ人は、むしろ不確実性を「変化が起きるからこそビジネスチャンスが生まれる」とポジティブに捉え、積極的に飛び込んでいきます。
Babson Collegeで提唱されているET&A(Entrepreneurial Thought & Action)の考え方(*10)では、不確実性やリスクを完全に排除するのではなく、「コントロール可能なリスク」に変えていくプロセスが重視されています。
例えば、今では広く使われている3Mのポストイット開発プロジェクトでは、当初は「接着力の弱い接着剤」という失敗作からスタートしたものの、「この“中途半端な粘着力”こそ新しい市場を生み出せるかもしれない」と、不確実性の中に可能性を見出し、小規模テストを経て大ヒット商品に育てました(*11)。
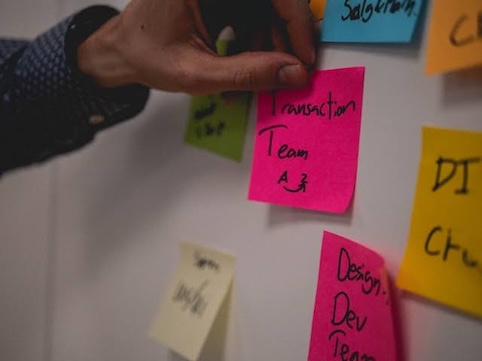
不確実性は避けるべきものではなく、“行動することで新たに得られる情報やリソースを活用して機会を切り開く”のがアントレプレナーシップ的な思考です。
小さく試して大きく育てる(Act, Learn, Build, Repeat)
ET&Aを体現するキーワードが、「Act, Learn, Build, Repeat」。いきなり完璧なビジネスプランを作るのではなく、小さく行動し、その結果から学び、次のビルド(改善)につなげる。そして、これを繰り返すことでビジネスを拡大していきます。
例えば、今では巨大企業であるAmazonも新しいサービスをリリースする際、初期段階ではミニマム機能だけに絞り込んだMVP(Minimum Viable Product)を出すことで、ユーザーの反応を素早くチェックして改善を繰り返しています。全社を挙げて巨大プロジェクトをドーンと作り込むのではなく、まずは小さくテストをしてフィードバックを得るというやり方を徹底しているのです(*12)。
「最初から100点満点の状態」を目指すのではなく、まず動いて学んでビルドし直す。このサイクルこそがイノベーションを生むアントレプレナーシップのポイントです。
「許容可能な損失(Affordable Loss)」を考える
リターンを最大化する考え方よりも、「最悪のシナリオでも自分(または組織)が耐えられる範囲の損失はどこまでか?」を明確にし、最初のチャレンジのハードルを下げていくのがET&Aの基本姿勢です。
大規模投資が必要なプロジェクトでも、イントレプレナーは「まずは●●円の範囲内で、●●人のリソースだけ使って試作してみる」というラインを設定し、それを超えない範囲でプロトタイプを作る。万一失敗しても組織的ダメージが小さいと示すことで、全社的な合意を取りやすくなります。
損失の最大許容範囲を把握し、その範囲内で行動を起こす。これにより、実践への一歩が踏み出しやすくなります。
既存のリソースを活かして行動する
起業家と聞くと「ゼロから何かを生み出す」イメージが強いですが、実は「自分(または組織)がすでに持っているリソースを最大限に活かす」考え方が重要です。リソースとは、人脈、知識、設備、技術、ブランドなど、目に見えないものも含まれます。
大手企業にリソースでは戦えないスタートアップでは、たとえ人脈や資金が乏しくても、大学の教授や先輩起業家とのつながり、学内の研究設備やコンテスト参加ルートなどが大きなリソースになります。
「リソースがない」とやらない理由を考えるのではなく、「持っているもの」を点検し、「今ある資源」を最大化する発想が、ゼロイチを手堅く成功に近づけるカギです。
失敗を前提に学び続ける
ET&Aでは「失敗はあって当然」と捉えます。小さい失敗を積み重ね、それを学びに変えながら改善していくプロセスこそが、最終的な成功へつながると考えます。
トヨタの「カイゼン活動」(*13)や、Googleの「失敗に対する寛容な文化」(*14)などが有名です。Googleでは、試験的なサービスがうまくいかない場合も、そこから得られたデータやノウハウを他のプロジェクトに転用し、次なるイノベーションの糧としています。
「失敗=終わり」ではなく、「失敗=学習データの蓄積」と考えることで、行動と検証を止めずに続けるのがアントレプレナーシップを持つ人の特徴です。
こうしたET&Aの要素は、イントレプレナーにも若手起業家にも共通して必要な思考とスキルです。大企業の保有リソースを最大限に活かしながら小さく実験を繰り返す方法もあれば、学生や若手の立場で限られた資源を上手く使って成長する道もあります。
不確実性を機会と捉え、まずは許容可能な範囲で行動を起こし、そこから学び続ける―この一連の流れこそが「起業家精神を持つ人の考え方とスキル」の本質なのです。
6.有名起業家に見るアントレプレナーシップを持つ人の考え方
アントレプレナーというと、ジェフ・ベゾスやスティーブ・ジョブスのような世界的な成功者の名前が思い浮かぶかもしれません。もちろん、彼らのような存在は極めて稀で、誰もがなれるわけではない──そう思われがちです。
しかし、彼らの言葉や行動の背景を見ていくと、成功の背後にあるのは「思考法」や「選択の習慣」であり、必ずしも天才的なひらめきや特別な才能だけではないことが見えてきます。
以下では、4人の有名起業家の名言を手がかりに、アントレプレナーシップに共通する“考え方”を読み解いていきます。これらは、新規事業に携わるすべての人にとって、日々の判断や行動を変えるヒントとなるはずです。
ジェフ・ベゾス(What choices will you make?)
Amazon創業者のジェフ・ベゾスは、起業に踏み切る際、自分が80歳になったときに「やりたいことをやらなかった後悔が一番大きい」と考え、金融業のキャリアや安定を捨てて一歩を踏み出しました。彼のエピソードは「日々、どのような選択をするかが、自分の人生を形作る」というメッセージを強く示しています(*15)。
この姿勢は、アントレプレナーシップの中核である自己決定性を象徴しています。たとえ成功する保証がなくても、「自分が信じる道を選ぶ勇気」が、新しい価値を生む出発点となります。企業内で挑戦を促す際にも、「目先の成功確率」だけでなく、「将来振り返ったときに意味ある選択か」を問う視点は重要です。
マーク・ザッカーバーグ(Facebook isn’t the first thing Built)
Facebook創業者のマーク・ザッカーバーグは、学生時代からさまざまなプロダクトをつくってきました。Facebookはそれらの“挑戦の一つ”に過ぎず、成功は偶然の積み重ねの中にあったと語っています。
このエピソードは、起業のリスクを限定的に捉えながら行動する「Affordable Loss(許容可能な損失)」という考え方と通じます。つまり、大きな勝算が見えてから動くのではなく、「失っても痛くない範囲」で実験し、そこから学ぶという姿勢です。
企業内でも、「成果が出るかわからないから止めておく」ではなく、「小さく始めてみよう」というスモールスタートの文化が、アントレプレナーシップの発露を後押しします。
スティーブ・ジョブス(Connecting the dots)
Appleを創業したスティーブ・ジョブスは、スタンフォード大学の卒業式スピーチで「Connecting the dots」という言葉を繰り返し伝えました。彼自身、大学中退後に興味を持ったカリグラフィ(書体)の授業が、後のMacintoshの美しいフォントやデザインにつながることを後から知り、すべての経験は何かしらの形でつながっていくと語っています(*17)。
今現在やっていることが、将来どのように活きるかはわからないものです。目の前の学びや経験は一見無駄に見えても、いつか「点が線でつながる」瞬間が来る。多様なインプットを積極的に取り入れ続ける姿勢こそが、イノベーションを生む土壌になります。
また、全ての経験が未来につながる、無駄なことはないと考えれば、許容範囲内の損失で色々と試してみることの必要性があると考えられるのではないでしょうか。
ドリュー・ヒューストン(You’re the average of the five people)
オンラインストレージサービス「Dropbox」の創業者ドリュー・ヒューストンは、「自分は周りにいる5人の平均だ」という言葉をしばしば引用し、環境の重要性を強調しています。どんな人と付き合い、どんなコミュニティに属するかが、自分の考え方や行動に大きく影響を与えるというのです(*18)。
アントレプレナーシップを高めるには、共感し合える仲間や刺激し合えるメンターがいるコミュニティに身を置くことが大切です。学内の起業サークルや大手企業の社内ベンチャーコミュニティなど、自分を取り巻く環境を意識して選ぶだけで、見える世界は大きく変わります。
この考え方は、「人が変わるには、周囲の人間関係が変わる必要がある」という環境要因の重要性を示しています。企業においても、挑戦する人が孤立しないように、挑戦者同士がつながれるコミュニティや場の設計が、アントレプレナーシップの育成には欠かせません。
7.アントレプレナーシップを育成するには
以下では、アントレプレナーシップ(起業家精神)を育成するための2つのアプローチをご紹介します。一つは大学などの教育機関を通じて体系的に学ぶ方法、もう一つは実際に企業での仕事を通じて現場感覚を身につける方法です。
大学などの教育機関で学ぶ
大学や大学院で体系的に学ぶことで、理論と実践を同時に身につけられるのが大きなメリットです。起業家として必要なマーケティングやファイナンス、ビジネスモデル構築の基礎に加え、リーダーシップやマネジメントスキルを磨くカリキュラムが用意されている学校も増えています。
例えば、上記でも紹介したBabson College(バブソン大学)は、アントレプレナーシップ教育に特化したビジネススクールとして非常に有名です。U.S. News & World Reportの「起業家精神を育む大学ランキング」で長年トップを獲得し続けており(*19)、実践的なプログラムが特徴です。学生は入学直後から自分たちでビジネスを起こし、リアルな市場で売上を立てながら学ぶ機会を得られます。
他にもスタンフォード大学やハーバード大学など、スタートアップのメッカとされるシリコンバレーやボストン周辺の大学でも、起業家コミュニティが非常に活発です。大学の起業サークル、ビジネスコンテスト、インキュベーション施設などが整備されており、在学中からリアルな起業経験を積む学生も少なくありません。一方、日本では、近年ようやくアントレプレナーシップ教育への関心が高まりつつあります。東京大学(*20)など一部の大学では、「本郷テックガレージ」などの拠点を活用して、学生や研究者が起業アイデアを形にする支援体制が整っています。また、起業家を招いた講義やピッチイベント、ベンチャーキャピタルとの連携プログラムもあり、実践的な学びとネットワーク形成が可能です。
とはいえ、アメリカと比べるとまだまだ文化的・制度的な壁があるのも事実です。「失敗への寛容さ」や「リスクを取ることへのポジティブな評価」が社会全体で十分に根付いていないため、学生が安心して起業に踏み出せる環境は発展途上にあります。そのため、教育機関には理論だけでなく、実践を通じて「挑戦するマインドセット」を養える場の提供が求められています。
企業で仕事を通じて学ぶ
もう一つのアプローチは、すでに成功している企業やコミュニティに身を置き、実践的にアントレプレナーシップを磨く方法です。特に米国では、起業家がある特定の企業でキャリアを積んだ後に独立し、自分の会社を立ち上げているケースが多く見られます。
「PayPalマフィア(PayPalから独立した起業家集団)」の例が有名ですが、PayPalで一緒に働いていたメンバーが後にYouTubeやTesla、LinkedInなどを創業したエピソードは、シリコンバレーのレジェンドとなっています。彼らは企業勤めの間にネットワークやノウハウを蓄積し、社内起業的なプロジェクトを通して実行力を磨いていました。
他にも、GoogleやAmazon、Microsoftなどの大企業出身者がスタートアップを立ち上げる動きも盛んです。実際に「米国の成功した起業家の多くが特定の企業出身である」というデータもあるように、スケールの大きい企業で最先端のビジネスを経験し、人脈と知識を蓄えたうえで起業するパターンは非常に合理的といえます。
8.アントレプレナーシップを発揮しやすい企業とその特徴とは?
先に紹介した「PayPalマフィア」や、時価総額10億ドルを超える企業の多くに共通するのは、「出身企業に一定の偏りがある」という事実です。著書『スーパーファウンダーズ』によると、ある期間においてユニコーン企業の創業者が最も多く在籍していた企業はGoogleであり、次にOracle、IBM、Yahoo、Facebook、Microsoft、Amazonと続きます(*21)。
日本でも、リクルート、サイバーエージェント、DeNAといった企業出身の起業家が目立っており、「起業家を輩出する企業には一定の共通点がある」と言われています。
このような企業の在り方を参考にすることで、アントレプレナーシップを内側から育むための環境整備や支援策について、いくつかのヒントが得られるのではないでしょうか。
以下では、特に注目すべき5つの観点をご紹介しながら、それぞれの文化的特徴が、企業内でどのように活かし得るかを考察します。
① 若手に裁量を与える文化:自律性が成長を促す
起業家を輩出する企業の多くは、若手であっても実際の意思決定や事業責任を持たせる文化を重視しています。たとえばGoogleでは有名な「20%ルール」によって、社員が自らのアイデアを追求できる時間が確保されており※(*22)実践を通じて意思決定力や問題解決能力が磨かれる環境があります。
これを企業内に適用するなら例えば、「新規事業プロジェクトの主担当者を思い切って若手に任せる」「小規模でもPL責任を持たせる」といった設計を取り入れるなどが考えられます。そうすることで将来の事業リーダーを社内から育てる土壌をつくることができるかもしれません。
② 社内にロールモデルがいる:共鳴が挑戦を引き出す
PayPalマフィアの事例に見られるように、社内に挑戦を楽しむ上司や、過去に独立・新規事業を経験した先輩社員がいることが、次の起業家を生み出す引き金となるケースは少なくありません。
このような観点から、自社の中で新規事業や異動経験を持つ人材を可視化し、若手との対話の場を創出するなど、「社内の挑戦者同士をつなぐ仕組みづくり」が、文化醸成に向けた一つのアプローチとなるでしょう。
③ 実験と失敗を許容する文化:挑戦の心理的ハードルを下げる
Amazonのジェフ・ベゾスは「失敗の数に比例して革新が生まれる」と語っています(*23)。実際に起業家を輩出している企業では、「まずやってみる」という姿勢が肯定され、失敗が評価やキャリアに直結しにくい環境が形成されています。
企業内においても、「失敗を“学び”として評価するカルチャー」を根付かせることは、挑戦者にとっての心理的安全性を高める重要な要素となります。たとえば、新規事業の評価制度に「仮説検証プロセス」を加味するなど、プロセス重視の視点を制度に組み込むことが一つの実践です。
④ 擬似的な起業経験を積める制度:経験から生まれる当事者意識
リクルートの「Ring」制度は、社員が年齢や職位に関係なく新規事業を提案・立ち上げできる環境として知られています(*24)。このような「社内起業」の経験が、実際に社外でも通用する起業的なスキルやマインドを育てている側面があります。
企業内でも、制度設計次第でこのような“ミニ起業”の体験は可能です。たとえば、一定期間の「新規事業チャレンジ枠」や、既存事業とは別にP/L責任を持てるサンドボックス的なプロジェクト枠の設定などが考えられます。
⑤ ミッションドリブンな環境:意味の共有が行動を駆動する
起業家を育む企業では、ミッションやビジョンが社員一人ひとりの行動の指針となっていることが多くあります。Googleの「世界中の情報を整理し、誰もがアクセスできるようにする」という明確なビジョンは、社員の主体的な行動を後押ししています(*25)。

(UnsplashのGreg Bullaが撮影した写真)
企業内の新規事業でも、「なぜこの領域に挑むのか」「自社にとってなぜ重要なのか」といったパーパスの共有は、メンバーの動機形成に不可欠です。顧客や市場の深い課題に深く触れた時にミッションが自分ごとになり新規事業の一担当者からイントレプレナーに変わるという論もあるように、事業やテーマの背景にある社会的意義を丁寧に伝えることは、アントレプレナーシップを引き出す第一歩となります。
9. まとめ:とにかく行動しよう!
アントレプレナーシップは生まれ持った才能ではなく、今必要な行動を実践し続ける態度・マインドセットです。そして、アントレプレナーシップのマインドセットは実践の中で育まれ、成長していきます。
新規事業推進の現場では、「起業家的人材がいない」「自走しない」といった声を耳にすることがあります。しかし、これまでの事例を振り返ると、アントレプレナーシップは必ずしも先天的な資質ではなく、「環境」や「文化」の中で磨かれるものでもあります。
本記事で紹介したような企業文化や制度設計は、そのような環境づくりのヒントとなり得ます。社内に眠る起業家的資質に火を灯し、新たな挑戦者を生み出すきっかけとなることを願っています。
Plug and Playでは、グローバルで大手企業500社以上のイノベーション創出を支援してきました。「人材育成」や「新規事業創出プログラム」などのアントレプレナーシップに関わる各種支援も提供しています。イノベーション創出やパートナー探索でお困りの企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。
それでは、最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。
Plug and Playに問い合わせる
参考文献
(*1) ピーター・ドラッカー『イノベーションと企業家精神』
(*2) Harvard Business Review: VUCA関連の記事
(*3) 新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』
(*4) U.S. Bureau of Labor Statistics, Entrepreneurship & Employment Data
(*5) Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2018/2019
(*6) Azoulayら(2018)”Age and High-Growth Entrepreneurship”, Harvard Business Review
(*7) Kauffman Foundation, “The Economic Case for Welcoming Immigrant Entrepreneurs“
(*8) 田所雅之『起業の科学』
(*9) Global Entrepreneurship Monitorレポート
(*10) Babson College公式サイト
(*11) 3M公式企業サイト(ポストイット)
(*12) エリック・リース『リーン・スタートアップ』
(*13) Jeffrey K. Liker『トヨタのカイゼン』
(*14) エリック・シュミット『How Google Works』
(*15) ジェフ・ベゾス『Invent and Wander』
(*16) デビッド・カークパトリック『フェイスブック 若き天才の野望』
(*17) Steve Jobs, Stanford University Commencement Speech (2005)
(*18) ティム・フェリス『Tools of Titans』
(*19) U.S. News & World Report「Best Colleges」
(*20) 東京大学「本郷テックガレージ」公式
(*21) Ali Tamaseb『スーパーファウンダーズ』
(*22) Inc. Magazine “Google’s 20 Percent Time“
(*23) Jeff Bezos’ Letter to Shareholders (Amazon)
(*24) リクルート『新規事業・ナレッジマネジメント』
(*25) サイモン・シネック『ミッションから始めよう』
