ディープテックスタートアップの成長は「採用」から加速する──センシンロボティクスが語るPlug and Playの活用術
2025/09/19
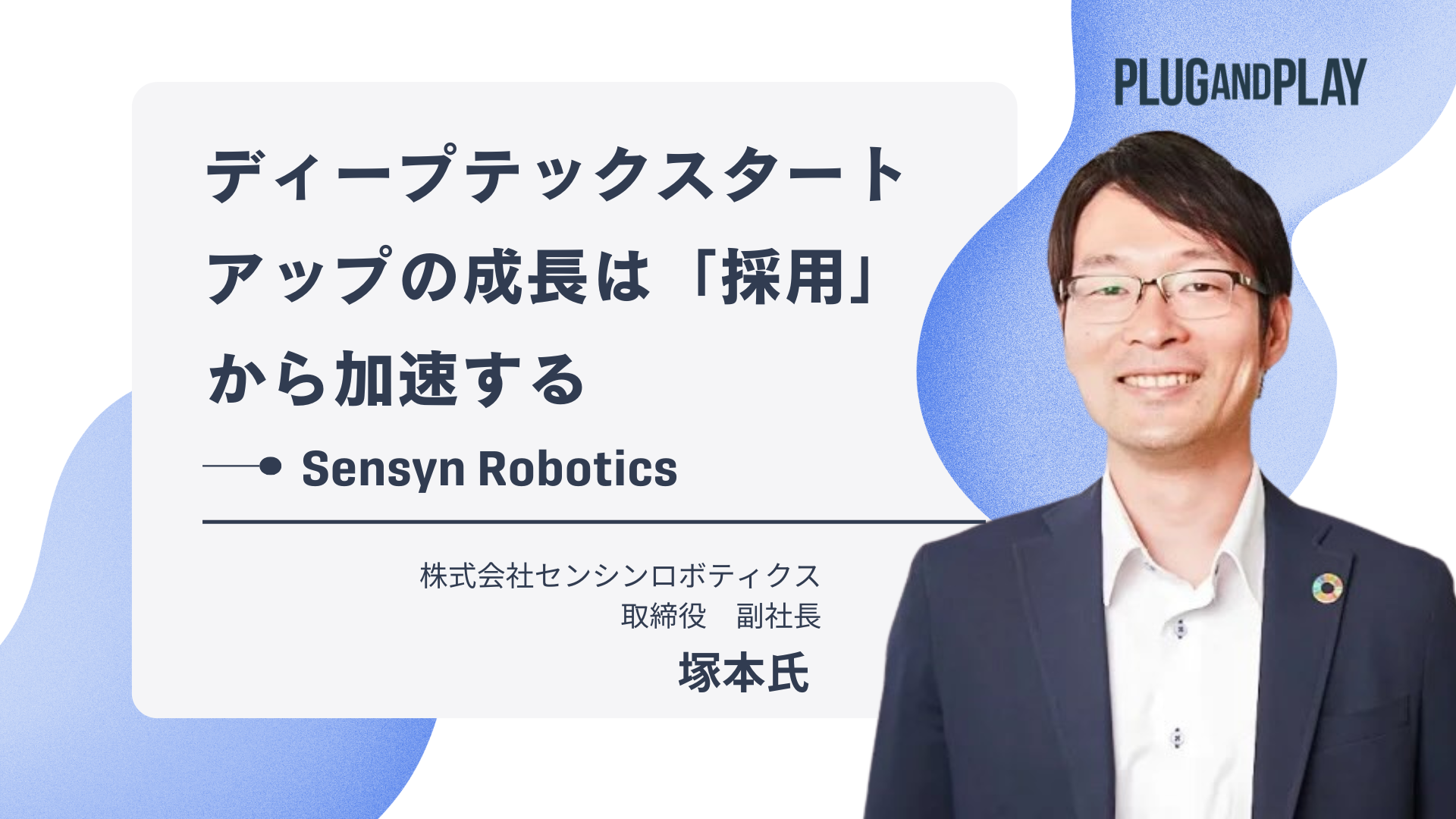
ディープテックのスタートアップは、誕生の瞬間から挑戦の連続です。技術を磨き、資金を集め、事業を軌道に乗せる——。その道のりは常に険しいものであり、 その中でも採用に課題を抱える企業も少なくありません。
高度な技術を社会実装しようとすればするほど、専門性の高い人材が必要になります。特に若手研究者や次世代のリーダー候補を見つけ、組織に根付かせることは一筋縄ではいかないものです。
当記事では、ディープテックスタートアップであるセンシンロボティクスがどのように採用の壁を始めとする事業課題を乗り越えたのか、その課題でどのようにPlug and Playを活用したのかを深掘りしていきます。
出会いは一通の誘いから
センシンロボティクスは、AIやロボット、IoTを活用し、社会インフラのDXを推進する企業です。石油、電力、建設といった巨大産業の「現場」に、最新テクノロジーを持ち込み、点検や保守の効率化に挑戦しています。
そんな同社がPlug and Playと出会ったのは、創業間もない頃。メンターからの一言をきっかけにプログラムに参加したのでした。
その後、海外展開を視野に入れた「グローバルプレパレーションコース」、スマートシティ関連のアクセラレーションプログラムなどに次々と選定されます。
「通常ならコールドコールから始めるような企業と、責任者レベルで話せる機会は非常に価値が高い。事業開発面で大きな前進がありました。また、企業側が課題を提示してくれる「リバースピッチ」という形式も、他のアクセラレータープログラムにはないユニークなもので、非常に良かったです。」
このように塚本さんはPlug and Playのプログラム内容を振り返ります。
イベントの舞台裏で起きたこと
2024年5月、塚本氏は株式会社アカリクとの共催イベント「Deeptech Career #4」に登壇します。会場は、熱気に包まれていました。登壇者はそれぞれ、研究者や学生に向けて、自社の挑戦やミッションを語ります。パネルディスカッションでは、未来のキャリアを模索する聴衆の真剣な眼差しが並びました。
イベント後の懇親会。塚本氏は、テーブルを回りながら学生たちに声をかけます。あるグループの中に、一人の大学院生がいました。話の流れで会社の話をし、互いの関心を深掘りしていくうちに、その学生からインターン生の募集がないかと尋ねられます。
「実はその当時、私たちはインターンを実施していませんでした。数年前に一度、新卒採用で組織の年齢構成を変えようと試みたのですが、新卒を受け入れるには教育コストや時間がかかるという課題に直面しました。その経験から、当時の会社の状況では新卒採用はまだ早いと判断し、一度トーンダウンしていました。」
しかし、この出会いが塚本氏の中で何かを動かしたと言います。

2024年5月24日開催 Deeptech Career #4 に登壇する塚本氏
「やってみよう」から始まった採用の再開
社内で役員や受け入れ部署と相談を重ね、「会社の雰囲気を変えるためにもやってみよう」とインターン受け入れを決断。その学生はエンジニアリングスキルを活かしながら新たな挑戦を楽しみ、やがて「新卒で入社したい」とまで言うようになりました。
これを契機に、同社は3名のインターン生を受け入れる体制を整えます。リモート中心の働き方に出社の機会が増え、ランチや雑談から生まれるコミュニケーションが組織を柔らかくしました。
「インターン生がいると、指導する側の若手メンバーも、教えることを通じて視座が上がりますし、彼らが会社に来てくれることで、リモートワーク中心の私たちも自然と出社する機会が増えました。インターン生を中心にランチに行ったり、顔を合わせて雑談したりと、社内の雰囲気作りにも繋がり、若手メンバーが入ってくることの良さを実感しました。」
若手の加入が想定以上の副次的な効果を生んだことで、R&Dチーム以外のフロントサイド、例えばプロジェクトマネージャーや営業、バックオフィスといった部門にも広げていきたいと考えていると言います。
「新卒や第二新卒といった若手メンバーを入れていかないと、年齢構成が変わりません。中堅層のメンバーが集まると、どうしても考え方が固定化しがちで、突拍子もないアイデアは出にくくなります。会社を変革する文化や風土の原動力となるのは若手人材だと思うので、積極的に採用していきたいです。今回のイベントをきっかけに道が開かれたと思っています。」
覚悟を決めた経営層の意思決定。この一歩が10年後を左右する
それでも、特にシードからミドルステージのスタートアップにとって、若手人材を受け入れて活躍させることにはリスクも伴うもの。若手採用を始めるには勇気がいります。タイミングを測っている間に、機会は過ぎ去ってしまうかもしれません。
「私たちも先輩のスタートアップ経営者に「新卒採用はいつから始めるべきか」とよく聞きますが、明確な答えはありません。色々な人に聞いた結果、結局は「経営陣が『採用する』と覚悟を決めるしかない」という結論に至りました。」
また、覚悟を決めて採用するからには、例えば多忙な部署に新卒を配属して放置するようなことがあってはいけないと言います。だからこそ、役員が率先して「これは会社としてやるべきことだ」という強い意志を全社に浸透させる必要があるのです。
「今回の新卒採用を決めた時も、社内で多くの方と議論をし、『この機会を逃してはいけない。このままでは10年後、我々は皆10歳年を取るだけだ』と説得しました。新卒採用をいつ始めるかは、結局誰かが決断するしかありません。その「決断」が何より重要だと思います。」
アカデミア人材とのタッチポイントは多くない。だからこそ
新卒採用の決断をしたら、後はどこで採用活動を行うか、という課題が生まれます。その点において、塚本氏はディープテック専門のキャリアイベントに参加したことに、手応えを掴んでいるようでした。
「このイベントは、アカデミアで学ぶ学生の方たちに、私たちのような会社があることを知ってもらえる貴重な機会です。そうしたアカデミア人材とのタッチポイントを創出するという意味で、「Deeptech Career」は私たちにとって非常に大きな意義があります。」
同社は、「Deeptech Career」を通じて学生には何を伝えたら魅力的に映るのか、シニア層を採用する時との違いを、肌感を持って知れたことを大きな収穫だと捉えていると言います。また、このような採用イベントは採用する企業側だけでなく、学生側に取ってもメリットが大きいと話します。
「また、学生にとっては、私たちのような未上場のスタートアップの事業内容を知る機会は、普段はほとんどないと思います。社名を検索して調べに来ない限り、情報に触れることはありません。キラリと光るようなスタートアップをまとめて知ることができる機会は、他にはないでしょう。私たちが他の登壇企業の方と知り合うことができたのと同じように、参加者の学生の方にとっても、同じような志を持つ同年代の仲間と知り合えることは、非常に価値があると思います。」
 2024年5月24日開催 Deeptech Career #4 の懇親会の様子
2024年5月24日開催 Deeptech Career #4 の懇親会の様子
(真ん中やや左、3人の学生と話しているのが塚本氏)
ディープテックの未来をつなぐ「Deeptech Career」
アカリクとPlug and Play Japanは、2022年から年2回のペースで「Deeptech Career」イベントを共催し、ディープテック領域の最前線で活躍する人々と、次世代を担う学生・若手研究者をつないできました。研究開発型スタートアップをはじめ、大手メーカーやVC、そして新卒入社一筋の方から起業経験者まで、幅広いバックグラウンドを持つ登壇者がリアルなキャリアを語る場です。
今回ご紹介したセンシンロボティクスの事例のように、このイベントは事業開発や採用のきっかけにもなり得ます。もしあなたが起業に関心を持っていたり、スタートアップやベンチャーキャピタルの世界に足を踏み入れたいと考えているなら、次はあなた自身がこのネットワークに加わる番かもしれません。
興味のある方はぜひ、次回のDeeptech Careerをご確認ください。
また、Plug and Playでは、起業や投資に関心のある方に向けたカジュアル相談窓口を設置しています。
ご希望の方は、下記フォームよりぜひお申し込みください。
