CVC設立からパートナー公募まで、“攻め”の協業で未来を描く島津製作所
2025/06/27

1875年の創業から150年、科学技術で幅広い産業分野の発展を支えてきた島津製作所。Plug and Playの企業パートナーでもある同社は2023年にCVCを設立するなど、近年はオープンイノベーションを通じた研究開発に力を入れています。その経緯や具体的な施策、Plug and Playとの連携の成果について「みらい戦略推進室」のメンバーにお話を伺いました。
Writer: Hideaki Fukui
Interviewee:
後藤 洋臣氏
基盤技術研究所 みらい戦略推進室 室長(写真中央)
橋爪 宣弥氏
基盤技術研究所 みらい戦略推進室 CVCグループ グループ長(写真左)
赤澤 礼子氏
基盤技術研究所 みらい戦略推進室 企画グループ 副グループ長(写真右)
全社展開を意識したオープンイノベーション戦略
ーー「みらい戦略推進室」では、どのようなオープンイノベーションに取り組んでいますか?
- 後藤氏:
私たちが所属する「みらい戦略推進室」は「全社視点での将来技術、新規事業の獲得戦略を立案し遂行する」というミッションのもと、社内の既存技術と社外の先進技術、そして社会課題と顧客ニーズを整理統合し、全社展開を意識したオープンイノベーションを展開しています。策定した戦略に基づいて技術獲得ポートフォリオを作成し、基盤技術研究所の研究ユニットと連携しながら技術獲得体制の構築および企画の実行を進める、というのがミッション遂行の大きな流れです。
これらのオープンイノベーションを推進するにはディープテック系を中心とするスタートアップとの出会いが不可欠で、2023年に設立したコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)や2024年にスタートした研究パートナー公募などの施策を通じてシナジーの期待できるスタートアップを日々発掘しています。
2023年3月に策定した全社の中期経営計画では「ヘルスケア」「グリーン」「マテリアル」「インダストリー」という4つの重点領域を定めていますが、「みらい戦略推進室」もこの4領域における社会価値創生を主目標としています。体制としては、具体的な新事業企画を考案する「企画グループ」、技術開発・事業開発を推進する「新事業開発グループ」、出資を通じた協業を担う「CVCグループ」の3グループで構成し、2025年4月時点で29名が所属しています。シリコンバレーにも2名のメンバーが駐在し、現地での事業開発や海外スタートアップ情報の収集を行っています。

(後藤氏)
ーースタートアップとの連携から生まれた成功事例はありますか?
- 橋爪氏:
直近の成功事例のひとつが、AIスタートアップであるエピストラ株式会社との共同開発から生まれた培養最適化支援ソフトウエア「CellTune」です。エピストラはライフサイエンス分野における実験の自動化や実験計画を最適化するAI技術に強みがあります。そこに弊社の分析技術などを組み合わせ、細胞培養条件の最適化ソリューションを共同開発するプロジェクトを2022年2月にスタートさせました。約2年半の開発期間を経て生まれたのが培養最適化支援ソフトウエア「CellTune」で、弊社の新たなリカーリング事業として今後の成長が期待されています。
もうひとつの例として、医療向けAIソフトウェア開発を行うエニシア株式会社の技術活用があります。京都大学発スタートアップのエニシアは、医療テキストを目的に応じて整理する独自言語処理技術を強みとしています。弊社では感染症を巡る主治医と専門医のコミュニケーションを円滑化する「感染症マネジメント支援システム」を名古屋大学などと共同開発していましたが、ここにエニシアのAI技術を応用したことで技術課題を乗り越えることができました。
- 後藤氏:
これまで弊社の新規事業開発には5年から10年という長い期間が必要でしたが、先の事例はいずれも3年ほどで市場投入に至っています。両社とはPlug and Playの紹介で出会い、社外技術の活用が開発期間短縮につながることを実感する好事例となりました。
ーースタートアップとの新規事業創出は非常に成功確率が低いというのが通念です。これらの事例の成功要因はどのあたりにあったのでしょうか?
- 後藤氏:
エニシアの場合は、もともと弊社の方で感染症マネジメントシステムを補完する技術を探索していたところに、医療ソフトウェア用のAI技術を持ったエニシアを紹介され、そこから話が進んだ形です。
- 橋爪氏:
エピストラは逆で、当初想定していなかった形での連携となりました。スタートアップが持つ技術を社内に共有したところ、複数のアイデアを検討し、その中の一つが実現に至った形です。オープンイノベーションという目的のもとで多様な可能性を探索でき、島津の社内からも積極的に新規事業のテーマを探索していた姿勢が、協業につながったのかなと思います。
「受け身の協業」から「戦略的な協業」へ
ーーオープンイノベーションを促進するための新しい取り組みはありますか?
- 赤澤氏:
私の所属する企画グループでは、昨年新たに研究パートナーの公募に取り組みました。これは、弊社から複数の研究テーマを提示し、興味を持ったスタートアップや研究機関からアイデアを募る、というものです。従来、共同研究のパートナーは紹介や学会でのマッチングが多かったのですが、より積極的に出会いを生むための施策として実施しました。これは会社として初の試みです。
今回は「老化抑制関連」「材料/プロセス開発支援」という2つのテーマを掲げ、「SHIMADZUみらい共創チャレンジ」のプログラム名で昨年11月に募集を開始。書類審査とヒアリング審査を経て今年4月に各テーマ1社ずつを採択し、共同研究に向けて動いているところです。募集に際しては、対象となるスタートアップや研究機関への告知と事前説明会の開催をPlug and Playにサポートいただきました。応募者の中には「この説明会で公募を知った」という方や、「説明会の参加者から聞いて知った」という方が多く、結果として充実したプログラムになったと感じています。
- 後藤氏:
それまでも研究者どうしがつながって共同研究を始めるような動きはありましたが、それを組織的な活動に落とし込めていなかった、という反省があります。この公募プログラムは、その課題を解消するモデルのひとつになったと思います。
- 赤澤氏:
そうですね。以前は社外からのオファーを受けて動き始める「受け身の協業」に甘んじており、グループ内でも「もっと戦略的に協業していきたい」という意見が出ていました。自ら発信してパートナーを見つける動きがこれまで少なかったので、今後は増やしていきたいと考えています。今年は島津製作所が保有するオープンイノベーション施設を活用したイベントなどを実施して、より多くのスタートアップに島津の取り組みを知ってもらう機会も作って行けたらと考えています。
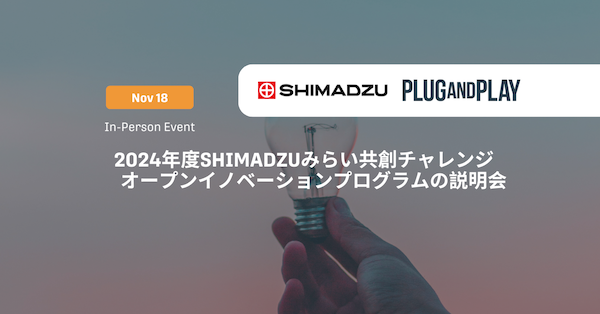
(2024年11月に開催したSHIMADZUみらい共創チャレンジ説明会)
スタートアップ連携のハードルを下げたCVC設立
ーーCVCを活用したスタートアップ連携について教えてください。
- 橋爪氏:
弊社では2023年4月に「Shimadzu Future Innovation Fund(Shimadzu FIF)」の名称でCVCを設立しました。同時期に発表された中期経営計画に盛り込まれた「7つの経営基盤強化」の中に「開発スピード強化」という項目があり、CVCもその施策の1つです。それ以前にも本体出資を通じたスタートアップ連携はありましたが、より迅速かつ効果的な連携の形を模索する中でCVCの設立に至りました。
もともと私は2020年1月から3年間、京都大学イノベーションキャピタル株式会社(京都iCAP)に出向し、ベンチャーキャピタルの業務を学んでいた経緯があります。そのためソーシングからデューデリジェンスといった一連の業務や、スタートアップ側の事情については一定の知見があり、それが設立時には役立ちました。
ファンドの形式としては、外部のベンチャーキャピタルであるグローバル・ブレイン株式会社と共同で運営しており、運用総額は50億円、運用期間を10年としています。投資領域としては中期経営計画でも重点化している「ヘルスケア」「グリーン」「マテリアル」「インダストリー」の4分野で、シード・アーリー期のディープテック系スタートアップが対象となります。
毎年2,000社ほどスクリーニングし、面談して投資検討をするのが1割ほど、実際に投資に至るのは1%未満です。設立から2年で計11社に投資を実行しましたが、現在の技術トレンドを反映してか、約半数がAIを基盤技術とするスタートアップです。AIは自社が持っていない技術なので、外部獲得の対象として重視しています。

(橋爪氏)
ーー共同研究や事業開発との向き合い方に変化はありましたか?
- 後藤氏:
CVC設立後の社内の変化として、全社的にスタートアップとの連携に前向きになったと感じています。もともと各事業部のメンバーはスタートアップとの接し方がわからなかったり、コミュニケーションを取るのが苦手だったり、という側面がありました。今は「間にCVCが入ってくれるから安心」という空気感があり、連携に至るまでの障壁が下がっています。特に海外スタートアップに関しては顕著にその傾向が表れています。協業だけが前提だと、事業部の求めているニーズとスタートアップの技術が一致しない場合に、そこでコミュニケーションが途絶えてしまうんですね。けれど、CVCであれば将来的な投資を前提にコミュニケーションを続けていくことができるので「有望だけれども今はタイミングが合わない」というスタートアップとも関係を継続できます。
また、私たち「基盤技術研究所」と各事業部とのコミュニケーションも活発になり、全社的にイノベーション機運が高まっているのを感じます。「スタートアップ」という言葉を社内でよく耳にするようになりましたね。
- 橋爪氏:
キャリアの充実という意味でも意義のある取り組みだと思います。私は研究畑を歩んできましたが、今は投資業務が中心です。社内にもベンチャー投資に関する専門知識を持つ人材が増えてきており、キャリア構築の多様性につながっています。
- 後藤氏:
私も研究者時代は一人で黙々と仕事をしていたものですが、新規事業に関わるようになってからは様々な現場に足を運んで自分の目で社会課題を見る機会が増えました。その過程で課題解決に取り組む姿勢も大きく変わりました。
- 赤澤氏:
私はオープンイノベーションに関わるようになって、島津製作所の事業の幅広さがよくわかりました。半導体からメドテック、ヘルステックまで、本当に幅広いことに挑戦できる会社だなと。弊社には興味のあるプロジェクトへの参画を希望できる社内公募制度があり、私のいる企画グループにも営業のメンバーが参加しています。研究所の業務に営業が参加するのは珍しく、それだけキャリアの選択肢が多い環境だといえます。

(赤澤氏)
グローバルなスタートアップ連携でさらなる価値創出を
ーーPlug and Playの企業パートナーとして、どのような利点を感じておられますか?
- 橋爪氏:
弊社がPlug and Playの企業パートナーになったのは2019年なので、6年ほどのお付き合いになります。主に協力いただいていることは3つ。ひとつはスタートアップとのマッチングで、CVCの運営においても有益なスタートアップ情報を提供していただいています。2つめは弊社のオープンイノベーション活動の情報発信や仲間集めの支援です。公募プログラムの事例でもお話した通り、基盤技術研究所や事業部の施策をスタートアップのコミュニティに広く周知していただいていますし、弊社施設を活用したイベントの開催なども企画の段階からご一緒しています。3つめが領域の調査で、特定の分野に関する技術調査、競合分析を依頼するケースも最近では増えています。クイックに市場全体の見極めや、協業候補企業の絞り込みができるという点で大いに活用させていただいています。

(2019年島津製作所本社内KYOLABSでのイベント開催の様子)
- 後藤氏:
特に海外スタートアップの情報に強い点が魅力だと感じています。海外のシード・アーリー期のディープテック系スタートアップは、VC経由で出会うことが難しく、グローバルに展開しているPlug and Playならではの強みではないでしょうか。立ち上がったばかりでまだ知られていないスタートアップをいち早く紹介してもらえる。今後もこの強みを生かしたサポートに期待しています。そして弊社もオープンイノベーションをより一層強化し、社是に掲げる「科学技術で社会に貢献する」というミッションを追求していきます。
